前回の記事で、私が専門学校を選ぶ時に基準になったポイントや入学までの気持ちの変化を書かせていただきました。
今回は入学して感じたことや、どのような1年制の専門学校がどのような授業内容だったかをざっくりと書きたいと思います。
専門学校に入学してまず感じたこと
専門学校に入学してまず感じたのは、「若い子が多いな」ということでした。もちろん社会人経験がある人もちらほらいましたが、割合でいえば8対2か9対1。ほとんどが高校を卒業したばかりの18歳前後の生徒でした。
やはり年齢も経験も違うので、最初は温度差を感じました。「このまま1年間やっていけるのだろうか‥」と不安になったことを覚えています。
製パンコースは30名弱で、女性の割合がやや多めでした。入学してすぐ自己紹介の場があり、私は次のように話しました。「最近まで自動車会社で働いていたこと。実家はパン屋だが知識はなく、一から学ぶために入学したこと。」
年齢も上で社会人経験もある私ですが、それは決して“偉い”わけではありません。むしろ謙虚な姿勢で、熱意は内に秘めながら、同じ仲間として肩を並べて学んでいくということを決めていました。
すると1週間も経たないうちに、自然とクラスに馴染んでいました。年齢の壁を意識することもなくなり、パンを学ぶ仲間としての一体感が生まれていったのです。
製パン実習で学んだこと(ざっくりまとめ)
実習の割合はおおよそ「製パン8割:製菓や調理2割」でした。
製パン実習では、まずパン作りの基本的な流れや工程を理解することを重視して学びました。最初の頃は手ごねで生地を作り、生地が出来ていく仕組みや感覚を体で覚えながら、発酵の見極めなども少しずつ学んでいきました。扱う生地はシンプルなものが中心で、バターロールやその生地を使った調理パンなど、一つの生地からさまざまなパンに展開できることも体験しました。
基礎を理解した後は、ミキサーを使った仕込みが中心に。私が通っていた学校では1班に1台のミキサーが用意されており、恵まれた環境の中で、食パン・バゲット・ブリオッシュ・カンパーニュなど、多彩な生地を仕込むことができました。特にバゲットはシンプルな材料でありながら焼き上げるのが難しく、その奥深さやシンプルな材料で無限に広がる美味しさに強く惹かれたのを覚えています。
後期に入ると、シーターを使ってクロワッサンの折り込みに挑戦。知識と技術が必要な作業でしたが、先生の指導や仲間の協力のおかげで、卒業する頃には生地作りから焼成まで自分の手で仕上げられるようになり、大きな成長を感じました。
また実習は主に4人班で進めることが多く、仲間と協力して作業を進める大切さも同時に学ぶことができました。
座学で学んだこと(ざっくりまとめ)
座学では、経営管理・公衆衛生・製パン理論などについて学びました。どれも現場に出た今でも役立つ内容だったと感じています。
経営管理では、収支計画や損益分岐点といった数字の見方を学びました。在学中はピンとこない部分もありましたが、のちにマネジメント業務に携わった際には、この基礎があったおかげでスムーズに理解することができました。
公衆衛生では、食品を扱ううえで欠かせない衛生管理の基本を学びました。「食べ物は人の体に入るものだから、時には命に関わる」ということを強く意識させられました。卒業後に取得した「食品衛生責任者」の資格講習でも改めて公衆衛生を学び、その重要性を実感しました。公衆衛生については日本食品衛生協会の「食品衛生責任者」ページも参考になります。
製パン理論では、小麦粉やイーストなど材料の性質や、パン科学実験を通じて理論を学びました。当時は「実習をやりたい」という気持ちの方が強かったのですが、現場に出てレシピを組み立てるようになってから、その知識の大切さを痛感しています。材料の特性を理解してこそ、それぞれの持つ可能性を最大限に引き出し、自分の理想の味に近づけることができるのだと感じています。
学びを通じて得られた気づき
今回の記事では専門学校で学んだ実習や座学について、ざっくりとご紹介しました。
実習では、パン作りの基本から少し難しい生地の仕込みまで幅広く取り組み、チームで役割を分担しながら作業を進める大切さも学びました。
座学では経営管理や製パン理論を通じて現場や実習での理解をさらに深めることができました。
また、在学中にはインターンの機会もあり、現場でしか得られない学びも経験しました。その内容については、別の記事で詳しく書いていこうと思います。
こうして先生方やインターン先の先輩方から多くを学び、技術だけでなく、人として・職人としての考え方も少しずつ育まれていったと感じています。
最後まで読んでいただきありがとうございます。今回は入学して感じたことや学びについてざっくりと書かせていただきました。少しでも参考になれば幸いです。


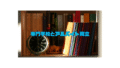
コメント